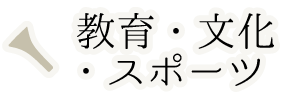令和7年度施政方針
令和7年五所川原市議会第2回定例会の開会に当たり、市政運営に関する基本方針について、所信の一端を申し述べます。
令和7年度は、新たな総合計画のスタートの年にあたり、将来像に掲げた2040年に向け、これからの5年間は非常に重要な年になると確信しております。
この5年間でしっかりとした土台を形成し、新たな将来像「市民ひとりひとりの『思い』で輝く五所川原」の実現のため、市民の皆様の思いを大切にし、市民一人ひとりが「自分にできること」を行って地域内でつながることで、相乗効果、いわばシナジーを生み出せるまちを目指してまいります。
それでは、令和7年度における主要な事業と施策の概要について、新たな総合計画の4つの柱に沿って申し上げます。
まず、1つ目の柱である「市民に寄り添った福祉の充実」についてです。
高齢者福祉において、認知症の方の増加が課題となっている中、市民一人ひとりが認知症への理解を深め、認知症の方やその家族が地域で安心して暮らせる社会を目指すために制定した「五所川原市認知症の人とともに生きるまちづくり条例」が4月に施行されます。
それと連動した取組として、認知症を予防するため、加齢性難聴に対する補聴器購入助成、認知症サポーターの養成講座による知識の普及と理解促進、さらに、人間としての尊厳を守るケア方法に関する講演会の開催などを通して、認知症に理解ある社会の実現を地域一丸となって目指してまいります。
また、全国的な課題である介護人材不足に対応していくため、外国人介護人材を受入れる介護施設への支援を実施し、高齢者の安全と安心を守り、自分らしい高齢期を実現できる社会を目指してまいります。
一方、子育て支援においては、核家族化や共働き世帯の増加に伴うライフスタイルの変化、地域の繋がりの希薄化などにより、子育て支援策の重要性が増しております。
子どもの医療費や学校給食費の無償化を継続し、子育て世帯の経済的負担を軽減するとともに、放課後児童クラブ延長利用料の助成を通年実施し、これまで実施してきた取組を生かしながら、子育てをする方の不安解消に努めてまいります。
障がい者福祉においては、総人口に対して、障がいを持つ方の割合は増加しており、誰もが自分らしく安心できるまちづくりのため、障がいに関する正しい知識の普及が重要となっています。
市民の障がいに関する正しい知識を深める機会を創出するとともに、障がいを持つ方の社会参加促進に向け、差別解消や合理的な配慮の理解をテーマとした展示会及びイベント開催を予定しており、誰一人取り残さない社会の実現に向け、障がい者福祉の推進に取り組んでまいります。
続いて、2つ目の柱である「地域の特色を生かした経済の活性化」についてです。
本市は、豊かな自然環境に恵まれ、悠久の歴史の中で多彩な人材や文化を育んできた地域であり、個性豊かな伝統文化や芸能を有しています。文豪・太宰治の生家として有名な「斜陽館」、中世の港湾都市である「十三湊(とさみなと)遺跡」など多くの魅力的な文化・観光資源を有し、それぞれの地域の人々が古くから守ってきた文化・魅力を継承していくとともに、それらが織りなす彩り豊かな魅力の発信を引き続き、推進してまいります。
中でも、本市の観光において、重要な役割を果たしている「立佞武多の館」のリニューアル工事がスタートします。令和8年夏のリニューアル後は、これまでの観光拠点施設としての機能を維持しつつ、「子どもの広場」、「中高生の居場所」の整備を行い、子ども達やその保護者など、市民も利用できる交流拠点として、更なる賑わい創出を目指し、世代を超えて市民が交流できる「コミュニティを体験できる交流拠点」としての機能を促進してまいります。
また、農業施策においては、農業経営の安定・拡大に向けた経営基盤の強化や新規就農者を含めた人材確保が喫緊の課題となっています。
そこで、新規就農者への支援や農業技術の継承により、新たな担い手の確保を継続して行ってまいります。さらに、施設園芸への参入、規模拡大や農作業の効率化に資するスマート農業、業務用野菜の生産など農業経営の収益向上に資する取組に対し、包括的な支援メニューを創設し、地域の担い手となる中心的な農家の育成を図ってまいります。
加えて、近年、りんごの病害虫被害が報告されています。産地が一体となった防除対策の取組を支援し、農家経営の安定化を図ってまいります。
物産振興においては、大町大通りを主会場とした「ホコ天マルシェ」、金木地域の特産品の代表格となる馬肉などの自慢の逸品を販売した「うまいもんフェスタinかなぎ」、道の駅「十三湖高原」を会場として十三湖産ヤマトシジミや市浦牛などの特産品をPRする絶好の機会となった「しうらグルメカーニバル」など市内の各地で民間主体で開催される物産イベントを支援することで、地域内での消費拡大を図るほか、本市の農林水産物の付加価値を高めるため、新商品開発の支援を行うとともに、ふるさと納税を通じて市産品の販路拡大を図ってまいります。
続いて、3つ目の柱である「豊かな教養を育む教育・人づくり」についてです。
学校教育においては、児童生徒数の減少によって、学校の小規模化に伴う教育環境の差が生じることなどが懸念されており、小学校と中学校との通学区域の関連性、学校と地域の結びつきを考慮し、学校の再編を進めております。
優先検討校である「三好小学校」では、令和7年4月の「五所川原小学校」との統合に向け、保護者や住民への説明会、児童の交流会などを進めてまいりました。「市浦小学校、市浦中学校」の再編については、本市初の併置校としての準備を進めており、引き続き、児童生徒数の減少等による諸課題を克服し、学びや育ちの質を高める教育環境の実現を推進してまいります。
また、多様化・複雑化する社会状況を背景に、いじめや不登校となる児童生徒が増加しており、その対応が難しくなっています。いじめの未然防止・早期発見並びに不登校対策のため、いじめ問題等対策協議会、不登校対策研修会などを定期的に開催し、学校現場、関係機関との情報共有、対応を協議していくことで、引き続き、全ての子どもが安心して共に学び、保護者にとっても信頼できる教育環境づくりを進めてまいります。
一方、生涯学習においては、子どもから大人まで全ての人が自発的に学習できる環境を提供していくことで、楽しく学び合いながら主体的に行動する力を育んでいく必要があります。
特に著しい人口減少が予測される本市においては、高齢者が、自分らしく、生き生きと活躍することが地域の活力に繋がることから、高齢者教室を引き続き開設することで、高齢者の自発的な学習機会の確保を図ってまいります。
また、子どもの地域での学びの場においては、中学校部活動の地域移行が喫緊の課題となっております。部活動は、地域のスポーツ・文化芸術の振興・発展を支えるとともに、心身の健全育成に大きな役割を担ってきました。
しかし、昨今の急速な少子化に伴う児童生徒数の減少等により、現在の部活動では、子ども達のニーズに対応できない状況や教職員の長時間勤務の一因になっていることから、地域のあらゆる関係者が連携し、地域住民全体で運営する部活動体制の構築が重要となっています。
子どもが自分らしく興味関心に打ち込む機会の確保、地域のスポーツ・文化芸術活動と一体的推進による多世代交流、生涯学習の充実へつなげていく「地域で支え地域が輝くスポーツ・文化芸術活動に親しむ環境づくり」を目標とし、地域住民が主体となる地域クラブへの移行を推進してまいります。
最後に、4つ目の柱である「将来を見据えた安全安心なまちづくり」についてです。
昨年は、各地で自然災害が頻発し、特に、令和6年能登半島地震では、三方を海に囲まれ、急峻な傾斜地が多いという半島地域特有の地理的要因によって、孤立地域の発生やライフラインの復旧においても大きな影響を及ぼしました。
本市においても津軽半島に位置することから、災害の脅威を強く認識し、昨年11月末には青森県知事とともに国の関係機関に対して防災体制の強化に係る要望活動を行ったところです。
引き続き、国、県と連携していくとともに、市としても条件不利な地域特性にあっても安心して暮らしていける環境を構築していくため、市浦地区沿岸部の防災無線設備の更新を行うことで、沿岸部の備えを強化し、災害に強いまちづくりを進めてまいります。
また、災害のみならず、生活圏における平時の安全安心の充実も重要なまちづくりの課題と認識しております。
五所川原駅前を起点とする市街地エリアは、「中心市街地活性化ビジョン」で示すとおり、この圏域における医療、行政、経済、観光、交通等の中心地として重要な役割を担っているため、引き続き、官民一体となったまちづくりの推進に取り組んでまいります。
また、少子高齢化、人口減少が進み、交通弱者の交通手段の確保が求められる中、公共交通機関の運転手不足、利用者の減少を起因とした採算性の低下などによりバス路線の減便や廃止がなされ、公共交通網の再構築が課題となっています。
そうした状況において、金木地域では、令和7年4月から公共ライドシェア「はいきたかなぎ」の乗降場所を追加し、利便性向上を図るほか、五所川原地域では、令和7年10月から市循環バスに変わる新たなAIデマンド交通の導入に加え、予約型乗り合いタクシーの再編を講じることで、引き続き市民の生活の足を確保してまいります。
子ども達の遊び場、子育て家庭のコミュニケーションの場としても重要な役割を果たしている公園の整備については、利用状況を踏まえ、優先順位をつけながら、安全の確保、利用環境の整備に取り組む必要があります。
金木地域の魅力向上において重要な役割を担っている芦野公園について、公園内の機能として重要な部分に優先順位をつけ、令和7年度は、危険木の調査、伐採を実施し、安全確保を図るとともに、桜の日当たりの妨げとなる樹木の伐採等を行い、公園の魅力向上に努めてまいります。
環境施策においては、地球温暖化対策実行計画区域施策編の策定を予定しています。2050年のゼロカーボンの実現に向け、地域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガス排出量の削減等を行うための施策を推進してまいります。
以上、令和7年度のスタートを迎えるに当たっての所信の一端と主要施策について申し述べましたが、厳しい財政状況においても、必要なものには、しっかりと重点化して投資し、将来の人口減少を見据えた持続可能なまちづくりに向け、着実な施策の推進を図ってまいります。
令和7年度は、新たな総合計画のスタートの年として、新たな将来像を目指し、市民の皆様と共に一人ひとりが輝くまちづくりを進めてまいりますので、市民の皆様、そして、議員各位におかれましては、引き続き、ご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げ、令和7年度の施政方針といたします。
問い合わせ先
担当 秘書課秘書係
電話 0173-35-2111
内線2131
内線2132