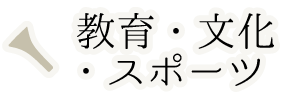乳幼児・児童の定期接種
予防接種について
お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、生後12か月までにほとんど失われていきます。
そのため、赤ちゃん自身で免疫をつくり、病気を予防する必要があり、その助けとなるのが予防接種です。
お子さんの健康を守るため、正しく理解し、かかりつけ医と相談したうえで予防接種を受けましょう。
定期接種について
定期接種は、法律によって予防接種の種類、対象年齢、接種期間、接種回数、接種間隔などが定められています。
接種料金
市民で対象年齢に該当する方は無料です。
対象年齢を過ぎたり、接種回数の間違いなどで受けた予防接種は定期接種にはならず、全額自己負担になりますのでご注意ください。
予防接種実施医療機関
接種するときは、必ず電話等で予約してください
また、予防接種には原則として保護者(父、母、養育者)の同伴が必要です。やむを得ず保護者が同伴できない場合は、お子さんの日頃の様子をよく知っている身内の方に同伴を委任することができます。その際には、予診票の同伴者記入欄(様式にない場合は、用紙の空白部分)に当日同伴する方の続柄と氏名を記入してください。
接種するときに持参するもの
母子健康手帳
母子健康手帳には、予防接種の接種歴を記録した大切なページがあり、医療機関では、同一ワクチンの接種回数の間違いや接種間隔の誤りなどから起こる健康被害を防ぐため、母子健康手帳で予防接種歴を確認しています。
予防接種事故を防ぎ、お子様の健康を守るため、予防接種を受けるときは必ず母子健康手帳を持参しましょう。
予診票
予診票は生後2か月頃までにご家庭に郵送します。
ただし、接種開始時期が小学生以上の予防接種については、次のタイミングでご家庭に郵送します。
・日本脳炎2期 小学3年生
・二種混合 小学5年生
・ヒトパピローマウイルス感染症 小学6年生
なお、転入された方で予防接種がお済みでない方、予診票紛失のため再交付希望の方は、五所川原市の予診票をお渡しします。交付方法は母子健康手帳をお持ちのうえ健康推進課までお越しいただくか、またはメール申請になります。詳細は下記リンク先のページに記載していますので、ご確認ください。
子どもの定期接種一覧
下記の予防接種名をクリックするとジャンプします。
※年齢の考え方:「○歳未満」「△歳から□歳に至るまで・達するまで」とは「○歳の誕生日の前日まで」「△歳の誕生日の前日から□歳の誕生日の前日まで」のことをさします。
・B型肝炎
・五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・Hib感染症)
・水痘
・日本脳炎
令和7年度五所川原市予防接種のお知らせチラシはこちらから (553KB)
(553KB)
ロタウイルス感染症
| ワクチンの種類 | 対象年齢 | 接種に望ましい接種期間 | 回数と接種間隔 |
|---|---|---|---|
| ロタリックス(1価) | 生後6週~24週 | 初回接種は、生後8週~14週6日まで | 27日以上の間隔をおいて2回経口投与 |
|
ロタテック (5価) |
生後6週~32週 | 初回接種は、生後8週~14週6日まで(1価と同じ) | 27日以上の間隔をおいて3回経口投与 |
- ワクチンの種類によって接種間隔が異なります。
B型肝炎
| 対象年齢 | 接種に望ましい接種期間 | 回数 | 接種間隔 | |
|---|---|---|---|---|
|
1歳に至るまで |
生後2~9か月に至るまでの期間 | 3回 | 2回目 | 1回目接種から27日以上の間隔をおいて接種 |
| 3回目 | 1回目接種から139日以上あけて3回目を接種(20週間後の同じ曜日から接種可能) | |||
- HBs抗原陽性の妊婦から生まれた乳児として、健康保険によりB型肝炎ワクチンの投与の一部または全部を受けた場合は対象外となります。
五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・Hib感染症)【令和6年4月1日から接種開始】
| 対象年齢 | 接種に望ましい接種期間 | 回数 | 接種間隔 | |
| 生後2か月~7歳6か月に至るまで | 初回 | 生後2か月~1歳に達するまで | 3回 | 20日以上の間隔で3回接種 |
| 追加 | 1期初回終了後、6か月以上(標準的には1年~1年半)の間隔をおく | 1回 | ||
- 令和6年2月以降に生まれた方は、原則、五種混合ワクチンで接種します。
- 四種混合ワクチンおよびHibワクチンで接種をしている場合不要です。
四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)
| 対象年齢 | 接種に望ましい接種期間 | 回数 | 接種間隔 | |
| 生後2か月~7歳6か月に至るまで |
初回 |
生後2か月~1歳に達するまで | 3回 | 20日以上の間隔で3回接種 |
| 追加 | 1期初回終了後、6か月以上(標準的には1年~1年半)の間隔をおく | 1回 | ||
- 五種混合ワクチンで接種した場合は接種不要です。
- 四種混合ワクチンは製造中止のため在庫限りの接種になります。Hib感染症ワクチンを完了し、四種混合ワクチンが未完了の方は、四種混合ワクチンでの接種になるので、接種間隔を守りながらお早めに接種ください。
- 三種混合ワクチンの残回数のある人は四種混合ワクチンで代替接種可能です。三種混合ワクチンの接種を希望される方は健康推進課へお問い合わせください。
Hib感染症(1回目の接種開始月齢により接種回数が異なります)
| 対象年齢 | 接種に望ましい接種期間 | 回数 | 接種間隔 | |
|---|---|---|---|---|
|
生後2か月~5歳に至るまで |
初回 | 生後2~7か月に至るまでに接種開始 | 3回 | 1歳になるまでに27日以上の間隔で3回接種 |
| 生後7か月~1歳に至るまでに接種開始 | 2回 | 1歳になるまでに27日以上の間隔で2回接種 | ||
| 追加 | 初回終了後7か月以上の間隔(標準的には7~13か月)おく | 1回 | ||
-
五種混合ワクチンで接種した場合は接種不要です。
- 1~5歳未満で初回接種を開始した場合は1回のみ接種します。
- 1歳を過ぎたら初回は行わず、最後の接種から27日以上あけて追加を接種します。
小児の肺炎球菌感染症(1回目の接種開始月齢により接種回数が異なる)
|
対象年齢 |
接種に望ましい接種期間 | 回数 | 接種間隔 | |
|---|---|---|---|---|
|
生後2か月~5歳に至るまで |
初回 | 生後2~7か月に至るまでに接種開始 | 3回 |
2歳になるまでに27日以上の間隔で3回接種 初回、2回目の接種が1歳以降の場合、3回目は接種しない |
| 生後7か月~1歳に至るまでに接種開始 | 2回 | 2歳になるまでに27日以上の間隔で2回接種 | ||
| 1~2歳に至るまでに接種開始 | 1回 | |||
| 追加 |
初回終了後60日以上の間隔をおいて、1歳に至った日以降に1回接種 (標準的には1歳~1歳3か月) |
1回 | ||
- 2~5歳未満で初回接種を開始した場合は1回のみ接種します。
- 2歳を過ぎたら初回は行わず、最後の接種から60日以上あけて追加を接種します。
BCG(結核)
|
対象年齢 |
接種に望ましい接種期間 | 回数 | |
|---|---|---|---|
| 1歳に至るまで | 生後5~8か月に達するまで | 1回 | |
麻しん・風しん二種混合
|
対象年齢 |
接種に望ましい接種期間 | 回数 | |
|---|---|---|---|
| 1~2歳に至るまで | 1期 | 1歳になったらなるべく早めに接種 | 1回 |
| 小学校就学前の1年間の小児 | 2期 | 5歳以上7歳未満のいわゆる幼稚園等の年長児 | 1回 |
- ワクチンの供給不足のため、令和6年度における麻しん・風しん定期接種の対象者は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間、接種対象期間を超えて接種可能です。
水痘
|
対象年齢 |
接種に望ましい接種期間 | 回数 | 接種間隔 | |
|---|---|---|---|---|
| 1~3歳に至るまで | 1歳~1歳3か月に至るまでに接種開始 | 2回 | 3か月以上(標準的には6か月から12か月)の間隔で2回 | |
日本脳炎
|
対象年齢 |
接種に望ましい接種期間 | 回数 | 接種間隔 | |
|---|---|---|---|---|
| 生後6か月~7歳6か月に至るまで | 1期初回 | 3~4歳に達するまで | 2回 | 6日以上の間隔で2回接種 |
| 1期追加 | 4~5歳に達するまで | 1回 | 1期初回終了後6か月以上の間隔をおいて接種 | |
| 9歳以上13歳未満 | 2期 | 9~10歳に達するまで | 1回 | |
- 平成17年度から平成21年度にかけての接種の積極的勧奨の差し控えにより、日本脳炎の予防接種を受ける機会を逃した人で、平成19年4月1日までに生まれた20歳未満の人は、不足回数分の接種を受けることができます。
二種混合(ジフテリア・破傷風)
|
対象年齢 |
接種に望ましい接種期間 | 回数 |
|---|---|---|
| 11歳以上13歳未満 | 11歳から12歳に達するまで | 1回 |
ヒトパピローマウイルス感染症
| 対象年齢 | 接種に望ましい接種期間 | 回数 | 接種間隔 | |
| 小学6年生~高校1年生に相当する年齢の女子 | 中学1年生 | 3回 | 2価ワクチン(サーバリックス) | 初回接種から1か月後に2回目、6か月後に3回目 |
| 3回 | 4価ワクチン(ガーダシル) | 初回接種から2か月後に2回目、6か月後に3回目 | ||
| 2回~3回 | 9価ワクチン(シルガード9) |
|
||
- ワクチンの種類で接種間隔が異なります(同一のワクチンを2~3回接種)。
- ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(定期接種)について詳しくはこちら

よくある質問
Q1 五所川原市外の病院で定期接種はできますか?
A1 定期接種は原則として、住民票のある市区町村での接種となっています。ただし、基礎疾患を有する等、やむを得ない事情により、県内他市町村または県外で定期接種を希望する場合で、市が必要と認めたときは、五所川原市外での定期接種が可能です。詳しくは健康推進課へお問い合わせください。
Q2 里帰り出産で、五所川原市に戻ってきました。五所川原市内の病院で子どもの予防接種をする場合にはどうしたらいいですか?
A2 ご本人や住所票のある市区町村から、五所川原市役所宛の依頼書等の提出は必要ありません。依頼書等は直接接種を希望する医療機関に提出のうえ接種をしてください。住所票のある市区町村によって住所地以外での予防接種の実施までの手続きが異なりますので、詳しくは住所票がある市区町村にお問い合わせください。
Q3 五所川原市に転入してきました。まだ接種していない定期接種があるのですが、どうしたらいいですか。
A3 接種を完了していない定期接種の五所川原市の予診票をお渡ししますので、母子健康手帳を持参のうえ健康推進課の窓口までお越しになるか、予防接種専用メールアドレスへ交付申請をしてください。接種間違いを防ぐため、母子健康手帳を確認してから予診票をお渡ししています。交付申請の方法は下記リンク先のページに記載しています。
Q4 予診票をなくしました。予診票はもらえますか?
A4 健康推進課の窓口まで、母子健康手帳を持ってお越しになるか、予防接種専用メールアドレスへ交付申請をしてください。接種間違いを防ぐため、母子健康手帳を確認してから予診票をお渡ししています。交付申請の方法はQ3のリンク先のページに記載しています。
Q5 長い間病気治療のため入院し、本来定期で接種できる期間を過ぎてしまいました。病気が治ったあとの接種は自己負担になりますか?
A5 原則として、定期接種の対象年齢期間を過ぎた場合の接種は自己負担となります。ただし、長期にわたる重篤な疾病等の理由により定期接種を受けられなかった方は、その特別な理由がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間は、接種対象年齢を超えていても接種できます。ただし、種類によっては定期接種できる年齢に制限があるものがありますのでご注意ください。詳しくは健康推進課へご相談ください。
Q6 市外へ転出することになりました。五所川原市から交付された定期接種予診票は、転出先の自治体でも使えますか?
A6 転出先から新たに予診票の交付を受ける必要があります。転出先自治体の予防接種の窓口へ必ずお問い合わせください。なお、転出後、当市で発行した予診票は使用できませんのでご注意ください。
問い合わせ先
担当 健康推進課健康政策係
電話 0173-35-2111
内線2372
内線2373
内線2374
内線2375