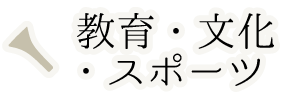介護(介護予防)サービスを利用するまでの手続き
介護(介護予防)サービスを利用するためには、五所川原市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。
窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決まります。
サービスを利用するまでの手続きの流れは以下のようになっています。
内容
要介護(要支援)認定申請
訪問調査
介護認定審査会
認定結果の通知
サービスの利用
要介護(要支援)認定申請
介護サービスを利用するためには、「要支援・要介護認定」の申請をすることが必要です。まずは五所川原市の担当窓口で申請の手続きをしてください。
- 新規申請
日常生活で介護や支援が必要になり、介護保険サービスの利用を希望する場合、申請することができます。
- 更新申請
要支援・要介護認定の有効期間満了日の60日前から要支援・要介護の更新の申請をすることができます。
- 区分変更申請
要支援・要介護認定の有効期間内であっても、状態の変化等により区分変更の申請をすることができます。
≪申請に必要なもの≫
- 介護保険認定申請書【Word
 (24KB)/PDF
(24KB)/PDF (193KB)】
(193KB)】 - 介護保険被保険者証
※紛失した場合は「介護保険認定申請書」内の被保険者証添付なしに☑をお願いします。
- 健康保険被保険者証の写し(第2号被保険者の場合)
≪申請手続きができる方≫
- 被保険者本人または家族
- 成年後見人
- 地域包括支援センター
- 指定居宅介護支援事業所
- 介護保険施設
※市内の指定居宅介護支援事業所、介護保険施設は「R8.2.10介護保険事業所一覧![]() (731KB)」をご覧ください。
(731KB)」をご覧ください。
郵送による申請も可能です。上記の申請に必要なものおよび資格者証送付用の返信用封筒(切手添付)を送付してください。なお、郵送の場合、届いた日が申請日となります。
訪問調査
調査員が自宅などを訪問し、心身の状況について本人と家族から聞き取り調査を行います。
介護認定審査会
訪問調査の結果と、特記事項、医師の意見書をもとに、介護認定審査会委員が介護認定審査会を開催し、どのくらいの介護が必要か(=要支援・要介護状態区分)を判定します。介護認定審査会では、介護の必要性について、総合的な審査判定を行います。(2次判定)
認定結果の通知
介護認定審査会の審査結果にもとづき、介護保険の対象とならない「非該当(自立)」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1~5」の区分に分けて認定され、その結果が記載された認定結果通知書と被保険者証が届きます。
・認定結果通知書に記載されていること
要介護状態区分、その理由、認定の有効期間など
・被保険者証に記載されていること
要介護状態区分、認定の有効期間、支給限度額、介護認定審査会の意見など
|
要介護状態区分 |
心身の状態の例 |
利用できるサービス |
|
要支援1・2 |
・食事や排泄はほとんど自分ででき、心身機能が改善する可能性が高い人 など |
介護予防サービス |
| 要介護1 |
・食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの世話の一部に介助が必要 ・立ち上がり等に支えが必要 など |
在宅サービス と 施設サービス |
| 要介護2 |
・食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要 ・立ち上がりや歩行に支えが必要 など |
|
| 要介護3 |
・食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない ・歩行が自分でできないことがある など |
|
| 要介護4 |
・食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない ・歩行が自分でできない ・問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある など |
|
| 要介護5 |
・食事や排泄、身の回りの世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない ・問題行動や全般的な理解の低下が見られることがある など |
非該当(自立)の場合、地域包括支援センターが中心となって行う介護予防事業(地域支援事業)や五所川原市が行う保健・福祉サービスなどが利用できます。
サービスの利用
「要支援1・2」と認定された方は介護予防サービスを、「要介護1~5」と認定された方は介護サービスを利用できます。
≪介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成≫
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。ケアプランとは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画のことです。介護保険のサービスを利用するときは、まず、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作成します。ケアプランに基づき、介護サービス事業所と契約を結び、サービスを利用します。
- 「要支援1・2」の場合(介護予防サービス計画書)
地域包括支援センターに相談
- 「要介護1~5」の場合(介護サービス計画書)
介護支援専門員(ケアマネージャー)のいる、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
※施設サービスの利用を希望する方は、施設へ直接申し込んでください。
※市内の各サービスの事業所は「介護保険事業所一覧」をご覧ください。
問い合わせ先
担当 介護福祉課介護福祉係
電話 0173-35-2111
内線2446
内線2447
内線2448
内線2449
内線2450
内線2452
内線2453