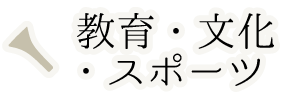後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度
『後期高齢者医療制度』の運営は、県内の40市町村すべてが加入した『青森県後期高齢者医療広域連合』が行い、保険料を決めたり、医療の給付などを行います。
また、市町村では、保険料の徴収や各種申請・届け出の受付などの窓口業務を行います。
対象者(被保険者)
資格確認書
届出
療養の給付
医療費の負担割合
自己負担限度額と高額療養費
75歳到達月の自己負担限度額の特例
入院時の食事代
療養病床に入院する場合の自己負担額
食事療養標準負担額(食事代)差額支給の申請について
高額医療・高額介護合算制度
保険料
保険料の納め方
対象者(被保険者)
1 青森県内に住所がある75歳以上の方
75歳の誕生日から対象です。
※被保険者となるための申請は不要です。ただし、被用者保険(会社の健康保険など)に加入されていた場合は、会社等で資格喪失の手続きが必要となりますのでご注意ください。
※青森県内の住所地特例施設に入居しているため、他都道府県の後期高齢者医療広域連合の被保険者である方については、この限りではありません。
※住所地特例施設とは、(1)病院又は診療所、(2)障害者支援施設、(3)独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設、(4)養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム、(5)有料老人ホーム、介護保険施設等です。
2 65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方
申請し、青森県後期高齢者医療広域連合の認定を受けた場合に被保険者となることができます。該当者には、65歳到来時、または各種手帳交付時に資格要件通知等を送付します。
【申請に必要なもの】 現在お使いの資格確認書または資格情報のお知らせ、障がいの程度がわかるもの、申請者の認印、マイナンバーカードまたは通知カード
※代理申請の場合、代理申請者の認印、身分証明書(マイナンバーカード等)も併せて持参してください。
3 青森県後期高齢者医療広域連合の被保険者で、他都道府県の住所地特例施設に転出された方
引き続き、青森県後期高齢者医療広域連合の被保険者となります。申請は不要です。
資格確認書
令和6年12月2日からこれまでの被保険者証が新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。
後期高齢者医療保険加入者の方には、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、全員に「資格確認書」が交付されます。(令和8年7月末までの暫定措置)
マイナ保険証での受付が困難な場合は、「資格確認書」でこれまで通りの医療を受けることができます。
また、75歳になる人には、誕生日の約1週間前までに「資格確認書」が郵送されます。
※マイナ保険証とは…保険証の利用登録をしているマイナンバーカード
届出
次のような場合は、届け出をしてください。
青森県外から転入
【届け出に必要なもの】
転出前の市町村から交付を受けた負担区分等証明書
※転出前の市町村より、被扶養者、障害認定、特定疾病についての証明書の交付をされている方は併せて持参してください。
青森県外へ転出
【届け出に必要なもの】
資格確認書、特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)、認印
青森県内の転入
【届け出に必要なもの】
なし
青森県内の転出
【届け出に必要なもの】
資格確認書、特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)、認印
市内の住所変更
【届け出に必要なもの】
資格確認書、特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)、認印
死亡したとき
【届け出に必要なもの】
資格確認書、特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)、認印
※ 申請により、葬儀を行った方に葬祭費(5万円)が支給されます。
【葬祭費支給申請に必要なもの】 葬儀を行った方の通帳、認印、葬儀を行ったかたがわかる書類
※葬儀を行った方に相続権がない場合、相続権を有する方の通帳、認印も併せて持参してください。
交通事故等にあったとき
【届け出に必要なもの】
資格確認書、第三者行為による被害届、交通事故証明書、事故発生状況報告書、認印など
交通事故等の他人の行為でけがをしたときの治療費は加害者の負担となりますが、届け出をすることにより後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。この場合、後期高齢者医療制度で治療費(医療給付分)を一時的に立て替え、後日、加害者に請求することとなります。
※届け出をする前に加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませていたりすると、後期高齢者医療制度で治療を受けられない場合がありますので、示談する前には必ず届け出をしてください。
療養の給付
次のような場合で、申請し、青森県後期高齢者医療広域連合が認めたときは、療養費として定められた額の払い戻しを受けることができます。
【申請に必要なもの】 資格確認書、診断書、領収書、通帳、認印、マイナンバーカードまたは通知カード
やむを得ない理由でいったん医療費を全額自己負担したとき
やむを得ない理由で医師の指示による転院などの移送に費用がかかったとき
治療のためコルセット等を作成したとき
医師の同意により、はり・きゅう・マッサージ等を受けたとき
※療養費は原則として本人の口座に払い戻しいたします。本人以外の家族の方の口座に払い戻しを求める際は、委任状が必要となりますのでお問い合わせください。
医療費の負担割合
医療機関等の窓口での自己負担割合は1割、2割、3割のいずれかとなっています。
判定のしかた
毎年8月1日現在の被保険者の属する世帯状況と被保険者の所得状況で判定しています。
現役並み所得者であれば3割、そうでなければ1割または2割となります。
ただし、現役並み所得者の方でも、申請(基準収入額適用申請)を行うことにより、負担割合が変わる場合があります。
|
※現役並み所得者 とは 住民税の課税所得が145万円以上の被保険者。 (またはその人と同一世帯の被保険者) |
次のいずれかに該当する場合は、申請(基準収入額適用申請)により申請日の翌月初日から1割または2割負担へ変更となります。
(1)同一世帯の被保険者全員の前年の収入額合計が520万円未満(被保険者が1人の場合は383万円未満)の場合
(2)同一世帯の被保険者(年収383万円以上)と70歳から74歳の人全員の前年の収入額合計が520万円未満の場合
【申請に必要なもの】 資格確認書、収入がわかるもの、認印、マイナンバーカードまたは通知カード
自己負担限度額と高額療養費
医療機関等の窓口で、1か月に支払った自己負担額が次の限度額を超えた場合は、申請により、超えた分が高額療養費として支給されます。
【申請に必要なもの】資格確認書、通帳、認印、マイナンバーカードまたは通知カード
※1度申請をすれば以後の申請が不要となり、高額療養費があるたびに自動的に支給されます。
※支給対象となる方で、過去に高額療養費の申請がない方には、青森県後期高齢者医療広域連合から、申請勧奨通知と申請書が郵送されます。
各負担内容と自己負担限度額
現役並み所得者3(課税所得690万円以上)
自己負担限度額(月額)…25万2,600円 + (医療費の総額 - 84万2,000円) × 1%
※該当後の過去1年以内に自己負担限度額(一般、低所得2、低所得1の期間は外来+入院の自己負担限度額)を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は14万100円になります。
現役並み所得者2(課税所得380万円以上690万円未満)
自己負担限度額(月額)…16万7,400円 + (医療費の総額 - 55万8,000円) × 1%
※該当後の過去1年以内に自己負担限度額(一般、低所得2、低所得1の期間は外来+入院の自己負担限度額)を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は9万3,000円になります。
現役並み所得者1(課税所得145万円以上380万円未満)
自己負担限度額(月額)…8万100円 + (医療費の総額 - 26万7,000円) × 1%
※該当後の過去1年以内に自己負担限度額(一般、低所得2、低所得1の期間は外来+入院の自己負担限度額)を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額は4万4,400円になります。
一般
| 負担内容 | 自己負担限度額 |
| 外来(個人ごと) | 1万8,000円 |
| 入院(世帯ごと) | 5万7,600円 |
※該当後の過去1年以内に4回以上、外来+入院の自己負担限度額を超えた場合、4回目以降の自己負担限度額は、4万4,400円となります。
※8月~翌7月までの1年間に、一般区分で受診した外来自己負担額合計が14万4,000円を超える場合には、高額療養費として支給されます。
※2割負担となる方には、令和4年10月1日から3年間は、外来診療における1か月の窓口負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置がありましたが、令和7年9月30日をもって終了しました。
令和7年10月1日からの外来診療の自己負担限度額は一律1万8,000円となります。
制度改正に関する問い合わせ
厚生労働省コールセンター 電話0120-117-571(受付時間 9時~18時 日・祝・年末年始を除く)
低所得2(市民税非課税の世帯に属する方)
| 負担内容 | 自己負担限度額 |
| 外来(個人ごと) | 8,000円 |
| 入院(世帯ごと) | 2万4,600円 |
低所得1(市民税非課税で、全員の各所得が0円(公的年金の場合は収入が年額80万円以下)である世帯に属する方および老齢福祉年金を受給している方)
| 負担内容 | 自己負担限度額 |
| 外来(個人ごと) | 8,000円 |
| 入院(世帯ごと) | 1万5,000円 |
※本項目以降掲載されている現役並み所得者3、現役並み所得者2、現役並み所得者1、低所得2、低所得1の数字は、いずれもローマ数字となります。
自己負担限度額について
自己負担額を限度額までとするには、マイナ保険証または限度区分が表記された資格確認書を医療機関等の窓口へ提示する必要があります。
75歳到達月の自己負担限度額の特例
月の初日以外の日に75歳に到達した方については、75歳到達月に限り自己負担限度額が半額となる特例があります。
入院時の食事代(食事療養標準負担額)
入院時の食事代は、医療費とは別に定額の自己負担があります。
自己負担額は、1食あたり510円です。
ただし、低所得2または低所得1に該当する方は、医療機関の窓口へマイナ保険証や限度区分が表記された資格確認書を提示することによって自己負担額が減額されます。
低所得2
減額後の負担額は次のとおりです。
ただし、低所得2該当後1年間の入院日数によって、1食当たりの自己負担額が変わります。
| 入院の日数 | 1食あたりの食事代 |
| 通算で90日までの入院 | 240円 |
| 通算で91日からの入院 | 190円 |
※91日目からの減額を適用するには、窓口で申請をする必要があります。
【申請に必要なもの】
資格確認書、入院日数を確認できる領収書、通帳、認印、マイナンバーカードまたは通知カード
低所得1
減額後の負担額は、1食あたり 110円です。
療養病床に入院する場合の自己負担額
療養病床に入院する場合、食費・居住費は介護保険と同様に利用者負担となります。 負担内容ごとの自己負担額は次のとおりです。
| 負担内容 | 自己負担額 |
| 食費 |
1食あたり510円 (医療機関によっては470円の場合があります。) |
| 居住費 | 1日あたり370円 |
低所得2または低所得1に該当する方は、医療機関の窓口へマイナ保険証または限度区分が表記された資格確認書を提示することによって自己負担額が減額されます。
低所得者2
負担内容と減額後の自己負担額は次のとおりです。
| 負担内容 | 自己負担額 |
| 食費 |
1食あたり240円 (医療の必要性の高い方は、入院日数90日超えで190円) |
| 居住費 | 1日あたり370円 |
低所得者1
負担内容と減額後の自己負担額は次のとおりです。
| 負担内容 | 自己負担額 |
| 食費 |
1食あたり140円 (医療の必要性の高い方は110円、老齢福祉年金の受給者の場合は110円) |
| 居住費 |
1日あたり370円 (老齢福祉年金の受給者の場合は無料) |
食事療養標準負担額(食事代)差額支給の申請について
限度区分が確認できるものを提示せずに医療機関へ食事代を多く支払った場合は、支払った食事代の差額支給を申請することができます。
【申請に必要なもの】
資格確認書、領収書、通帳、認印、マイナンバーカードまたは通知カード
※食事療養標準負担額差額は原則として本人の口座に払い戻しいたします。本人以外の家族の方の口座に払い戻しを求める際は、委任状が必要となりますのでお問い合わせください。
高額医療・高額介護合算制度
医療と介護保険サービスの両方を利用している世帯の負担を軽減するための制度です。
この制度は、同世帯内の被保険者全員が1年間(8月~翌年7月末)に支払った医療保険・介護保険の自己負担合計額から、次の自己負担限度額を差し引いた後の額を申請により支給します。(ただし、支給額が500円を超えないと支給されません。)
※支給対象となる方については、青森県後期高齢者医療広域連合から、毎年2月末頃にお知らせと申請書が郵送されます。また、青森県重度心身障害者医療費助成事業対象者については、委任状も併せて郵送されます。ご確認ください。
【申請に必要なもの】
資格確認書、通帳、認印、重度心身障害者医療費助成受給者用委任状、マイナンバーカードまたは通知カード
※高額医療・高額介護合算は原則として被保険者の口座に払い戻しいたします。申請時点で被保険者本人がすでに死亡している場合は受領申立書の提出が必要です。ただし、事前に葬祭費の申請等を行っているなど、受領申立書をすでに提出されている場合は不要です。被保険者以外の方の口座に払い戻しを求める際はその方の本人確認書類等が必要となりますので、事前にお問い合わせください。
※領収書は必要ありません。
※支給額の計算期間内に後期高齢者医療制度以外の保険加入期間がある方や、転入した方は、「自己負担額証明書」が必要になる場合があります。このようなときは事前にお問い合せください。
自己負担限度額は次のとおりです。
現役並み所得者3(課税所得690万円以上)
自己負担限度額は、年額 212万円です。
現役並み所得者2(課税所得380万円以上、690万円未満)
自己負担限度額は、年額 141万円です。
現役並み所得者1(課税所得145万円以上、380万円未満)
自己負担限度額は、年額 67万円です。
一般
自己負担限度額は、年額 56万円です。
低所得者2
自己負担限度額は、年額 31万円です。
低所得者1
自己負担限度額は、年額 19万円です。
保険料
被保険者一人ひとりに納めていただくことになります。
保険料額は、青森県後期高齢者医療広域連合が次の方法により計算します。保険料額を決める基準については、2年ごとに設定され、青森県後期高齢者医療広域連合内で原則均一となります。
令和6・7年度の保険料について
少子高齢化が進み、後期高齢者の医療費が今後さらに増加すると見込まれる中、すべての国民が年齢に関わりなく、負担能力に応じて医療保険制度を公平に支え合うため、令和6年4月から次のとおり制度が改正され、令和6・7年度の保険料に反映されています。
①後期高齢者医療給付費に占める、1人当たりの「後期高齢者の保険料」と「現役世代が負担する支援金」の伸び率が同じになるよう見直し
②出産育児一時金の費用の一部を後期高齢者の保険料から支援する仕組みの導入
制度改正の詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
保険料額の決め方(年額)
保険料額(年額)= 均等割額 + 所得割額
※100円未満切捨て
※保険料の賦課期日は毎年4月1日。ただし年度途中で資格を取得した場合は、資格取得日。
均等割額、所得割額はそれぞれ次のように求めます。
(1)均等割額の求めかた
均等割額は、被保険者1人当たり 4万6,800円です。
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額をもとに、均等割額を軽減するかどうか判定します。
| 世帯の総所得金額等の合計額 |
軽減後の額 (軽減割合) |
|
43万円+10万円×(年金・給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
1万4,040円 (7割軽減) |
|
43万円+(30.5万円×被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
2万3,400円 (5割軽減) |
|
43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(年金・給与所得者等の数-1)以下の世帯 |
3万7,440円 (2割軽減) |
※65歳以上の方の公的年金所得については、その所得からさらに高齢者特別控除15万円を差し引いた額で判定します。
(2)所得割額の求め方
被保険者の総所得金額等から基礎控除額43万(合計所得金額が2,400万円以下の場合)を差し引いた額に、青森県の所得割率9.90パーセントをかけた額です。
(3)保険料の賦課限度額
年間保険料は80万円が上限です。
制度加入直前に被用者保険(会社の健康保険等)の被扶養者であった人の保険料の特例
制度加入直前に被用者保険の被扶養者であった方は、均等割額のみで資格取得後2年間は 2万3,400円(5割軽減)となります。
※世帯の所得が低い方は、より高い均等割額の軽減(7割軽減)が受けられます。
保険料の納め方
保険料の納付方法は、原則として年金(年額18万円以上の方)からの天引きとなっています。(特別徴収)
年金額が年額18万円未満の方や介護保険料とこの制度の保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える方は、納付書や口座振替等で納めていただきます。(普通徴収)
口座振替での納付を希望する場合の手続きのしかた
【手続きの場所等】
市内金融機関、ゆうちょ銀行など
【手続きに必要なもの】
通帳、通帳の届け出印
※市外金融機関での口座振替手続きについては、取り扱っていない金融機関もありますので、ご確認の上お手続きください。
※すでに後期高齢者医療保険料以外の市税などで口座振替の手続きをしている方でも、新たに手続きが必要です。
※月末に手続きされた場合は、翌々月からの口座振替となる場合があります。
保険料の滞納
平成30年度分の保険料より延滞金の徴収を行っています。
延滞金については、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、納期限までに納めるべき金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付することになります。
※計算した延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。また、100円未満の端数は切り捨てます。
保険料の納付相談
後期高齢者医療保険料の納付が困難な方のために、納付相談を実施しておりますので、お気軽にお問合せください。
問い合わせ先
担当 国保年金課後期高齢者医療係
電話 0173-35-2111
内線2345
内線2346
内線2347