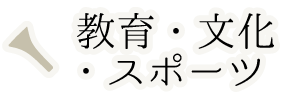保険料の決め方と納め方
保険料の決め方と納め方
●1号被保険者の保険料の決め方
介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)と第2号被保険者(40歳から64歳の方)とは、介護保険料の決め方、納め方が異なっています。
介護保険制度は、介護サービスに必要な費用を公費(50%)、第1号被保険者の保険料(23%)、第2号被保険者の保険料(27%)を財源に運営されています。
第1号被保険者の介護保険料は、当市の介護サービスに必要な費用から「基準額」を算出しています。
65歳以上の方の介護保険料基準額は、当市の介護保険事業計画における介護サービスに必要な費用の見込に基づき算出され、条例で定められています。 令和6~8年度(2024~2026年度)の介護保険料基準額は82,800円(年額)6,900円(月額)です。
一人ひとりの介護保険料額は、本人の所得や同じ世帯の住民税課税状況などによって、下記の表のとおり13段階に分かれます。介護保険料基準額82,800円に各段階の料率をかけて、各段階の保険料額が決まっています。
※令和7年度から保険料算定基準額が年金収入等809,000円となっております。
令和7~8年度介護保険料一覧
|
|
|
「老齢福祉年金」とは、明治44年(1911年)4月1日以前に生まれた方などで、他の年金を受給できない方等に支給される年金です。
上表の公的年金等には、遺族年金、障害年金などの非課税年金は含みません。
「合計所得金額」とは、年金、給与等の収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額の合計です(扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、基礎控除等の所得控除をする前の金額です。)。なお、合計所得金額が0円を下回った場合は、0円とみなします。
●1号被保険者の保険料の納め方
納め方は、特別徴収(年金からの天引き)と普通徴収(口座振替、納付書払い)の二通りがあり、年金受給者の場合は、原則、特別徴収による納め方が優先されます。
本人の希望で特別徴収と普通徴収との選択をすることはできません。
○特別徴収(年金からの天引き)
老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金を月額1万5千円(年額18万円)以上受給されている方は、年金からの天引きにより介護保険料を納めていただきます(老齢福祉年金からは天引きされません)。
ただし、対象となる年金を受給されている方でも、次の方は一時的に普通徴収(口座振替、納付書払い)にて納めていただく場合があります。
65歳になってからの一定期間
他の市町村から転入した場合
年度途中で保険料に増減があった場合
年金を担保として融資を受けた場合 等
○普通徴収(口座振替もしくは納付書払い)
老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金が月額1万5千円(年額18万円) に満たない方、または年金から天引きされない方は、納付書で納めていただきます。口座振替で納めていただくことも可能です。
口座振替は預貯金口座から自動的に引き落とされるので、納めに行く手間と時間が省け、納め忘れがありません。
手続きは、ご利用の金融機関窓口で行うことができます。
保険料を滞納すると、介護サービス利用時に不利益が生じる場合がありますので、 納め忘れにご注意ください。
●2号被保険者の保険料の決め方
40歳から64歳までの方の介護保険料は、加入している医療保険者ごとに保険料額を決定します。一人ひとりの介護保険料額は給料や所得に応じて計算されます。
40歳から64歳までの方の介護保険料については、加入されている医療保険者にお問合せください。
当市の国民健康保険に加入されている方は、国保年金課にお問合せください。
●2号被保険者の保険料の納め方
40歳から64歳までの方の介護保険料は、医療保険の保険料と一緒に徴収されます。
保険料を滞納すると、第1号被保険者と同様、介護サービス利用時に不利益が生じる場合がありますので、 納め忘れにご注意ください。
問い合わせ先
担当 介護福祉課介護福祉係
電話 0173-35-2111
内線2442
内線2443